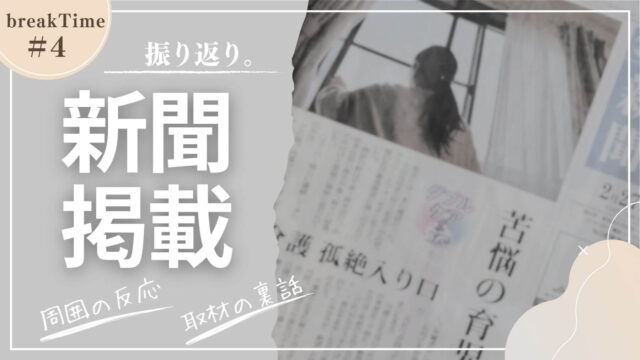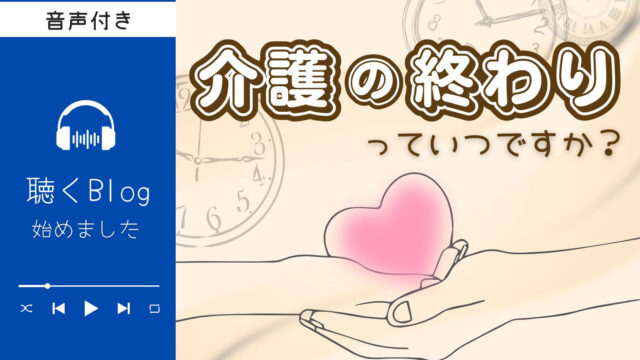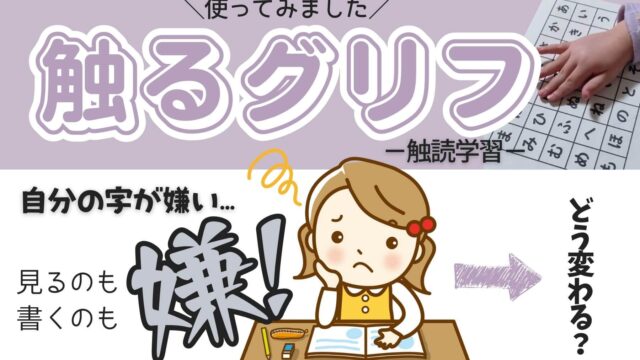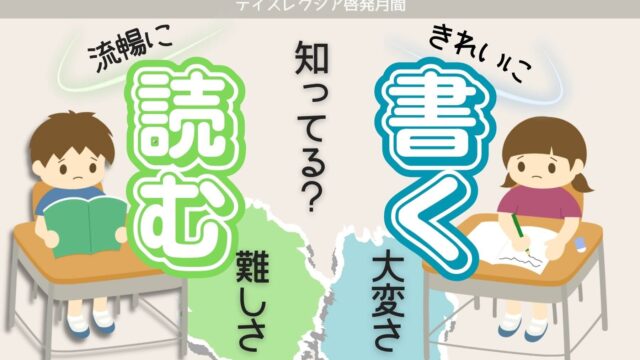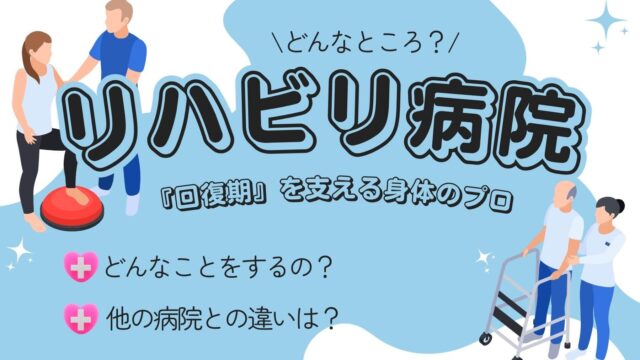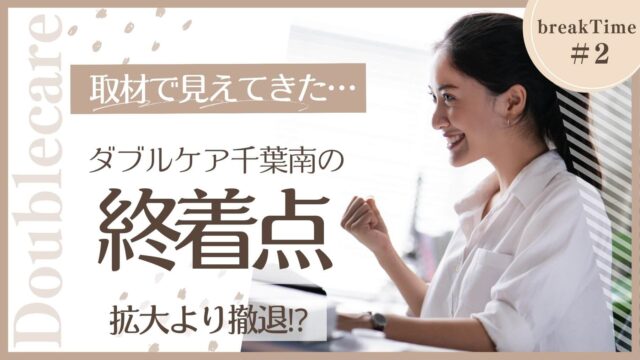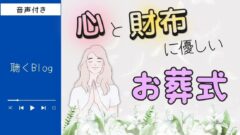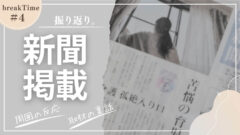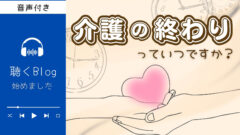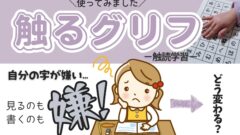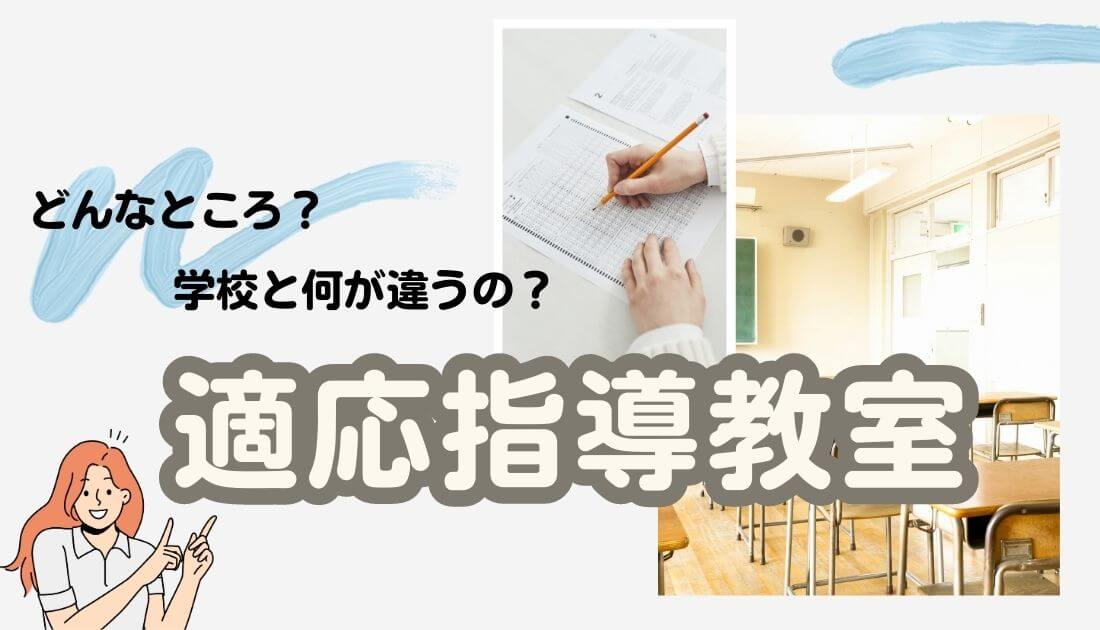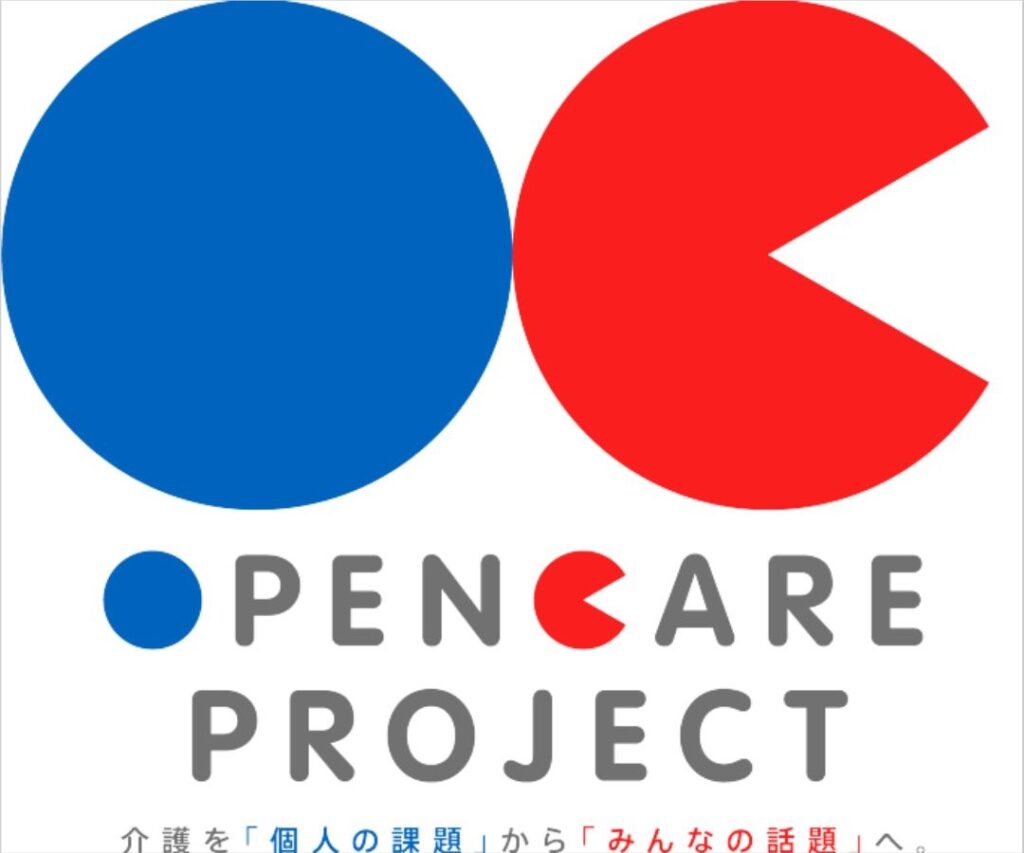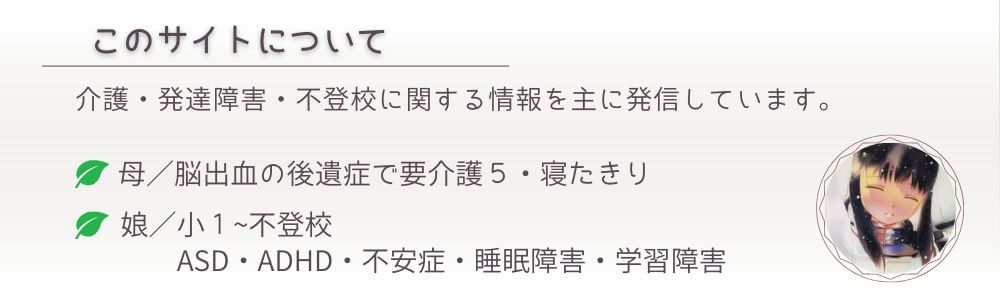

毎日新聞に掲載されました
ダブルケアカフェを開催しました
Stand. fmで対談しました
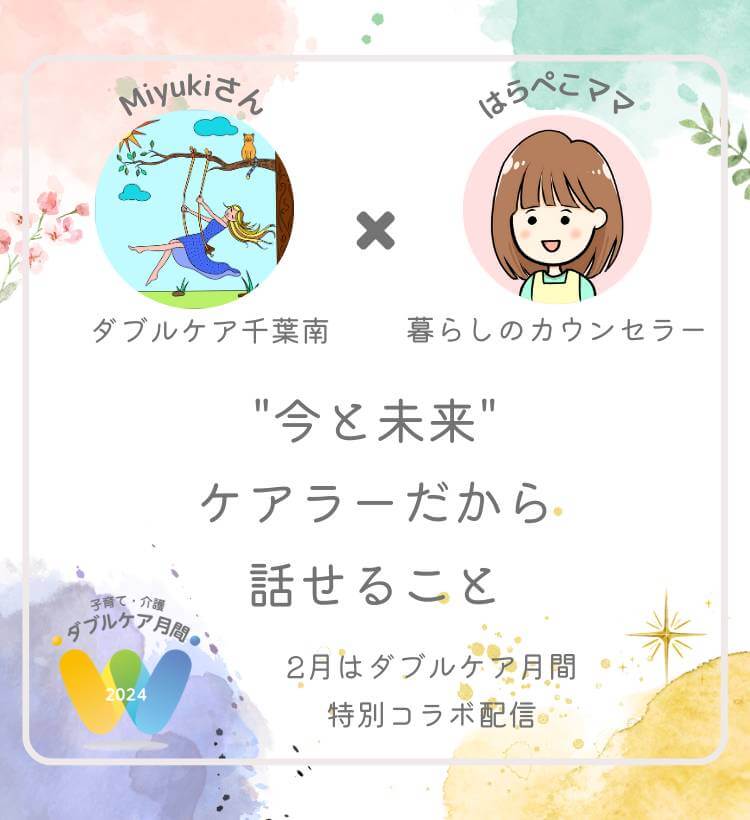
New Arrivals
‐新着記事‐
Popular
‐人気記事‐
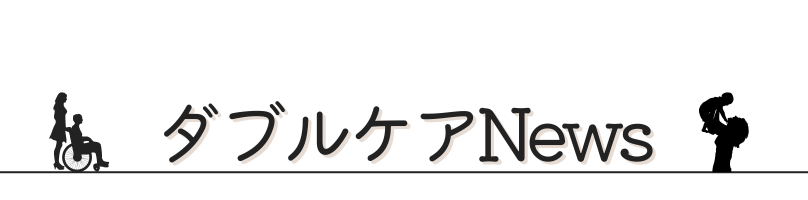
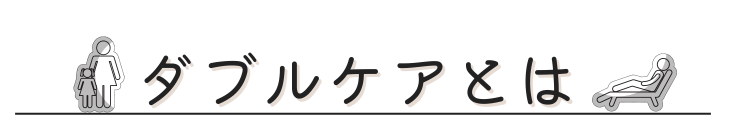
複数のケアが必要な状態を表す言葉です。
「親の介護と子育て」を同時期に担うことによく使われていますが
「家族の闘病と子育て」
「自分の闘病と子育て」
「義理の親と自分の親の介護」など
ダブルケアの定義やカタチは様々です。
さらに、
「親の介護 + 子育て + 自分の闘病」
等のトリプルケアというケースもあります。
また、ダブルケアにおける
「介護」は身体介護だけではありません。
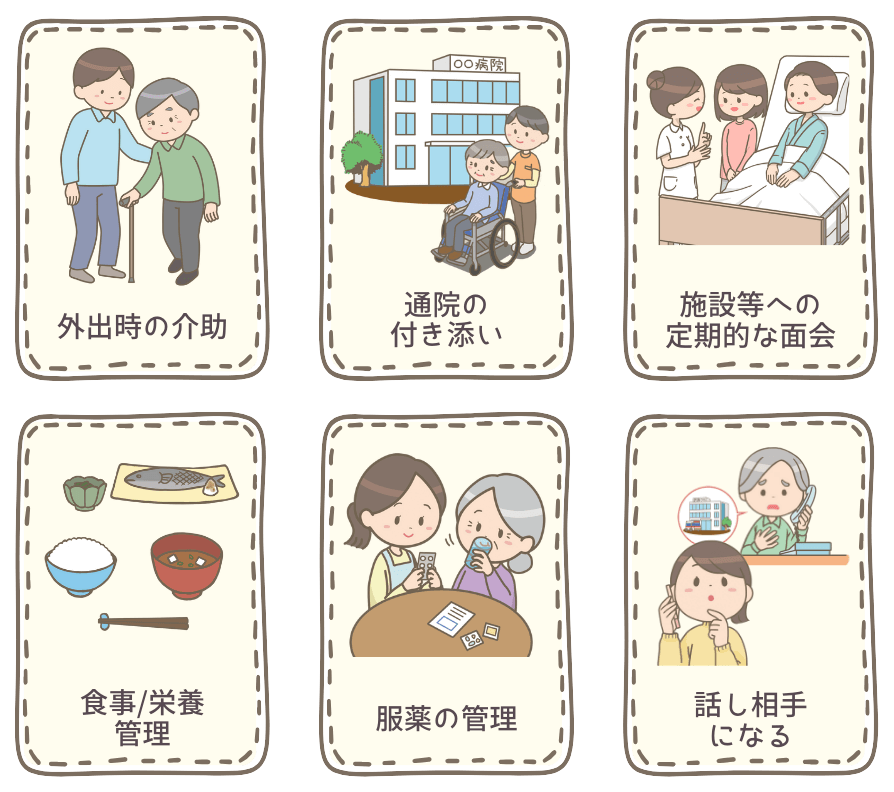
これらの身の回りのお世話も含まれます。
もし明日、ダブルケアになったら…
仕事は続けられるでしょうか?
ケアを担える人は身内に何人いますか?
メインのケアは誰が担いますか?
親は介護費用を用意していますか?
ダブルケアは誰にでも起こり得ることです。
介護が必要になってから考えるのではなく、介護を見据えて前もって家族で話し合っておくことが大切です。
元気な時だからこそ出来ることがある。
元気な時にしか出来ないこともある。
大切な家族のために「今」出来ることを。
当団体は、特定の法人・政治団体・その他団体等との営利関係は一切ございません。
また、開催するいかなるイベントにおいても、営業や情報収集目的でのご参加は固くお断りしております。
ケアラーの方々に安心して利用頂くためにも、ご理解とご協力をお願い致します。