※雑記カテゴリーは、気持ちをただ書き連ねる「息抜きの場」にしたいと思っています。
他の記事とは違い、砕けた文章になりますが、ご理解下さい。
2月、ダブルケア月間を走り抜いて、燃え尽きていた私。
気づけば5月も後半。
なかなかのブログの放置っぷりに自分でも驚いています(笑)
最近、ようやく書きたいことが少しずつ出てきたので、順次、仕上げていこうと思っています。(いつ仕上がるかはわかりません😅)
今回は、今更ながら、2月に毎日新聞に掲載された新聞記事について、諸々と振り返ってみようと思います。
記者ってすごい!

母は週5で介護サービスが入っており、取材に対応できる日がそもそも限られていました。
住んでいる場所も、決して交通の便がいいとは言えない場所なので、あまりにも手間や時間がかかり過ぎるのでは?と感じ、当初はオンライン取材を私から提案していましたが、奇跡的に予定が合い、家に招いての取材を実施することとなりました。
しかし、直前で、問題が発生します。
取材の数日前に大雨が降り、線路上で大規模な土砂崩れが発生したことで、電車が不通になってしまったのです。
被害状況からして、取材予定日までに復旧するのは絶望的でしたが、奇跡が起きます。
予定を前倒しして、取材当日の朝から徐行運転が開始されたのです。
こうして、無事に記者さんを自宅へお招きしての取材が実現しました。
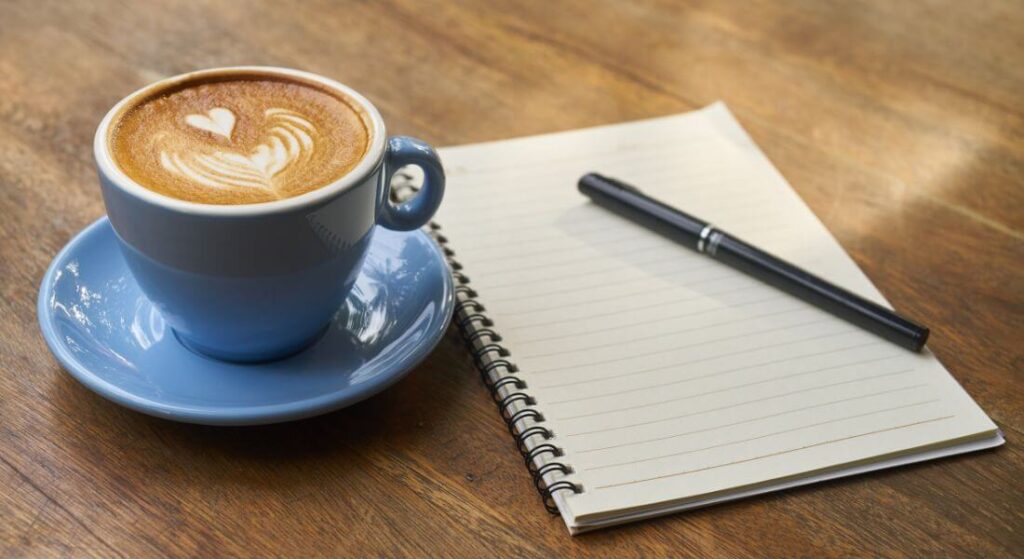
ちなみに、私の取材をしてくれた記者さんは、若い女性の方でした。
新聞記者というと、男性で、ちょっと強引に話を押し進めるような…
正直あまりいいイメージがなかったので、安心して取材を受けることが出来ました。
人見知りの激しい娘も嫌がることもなく、むしろ娘が記者さんに話しかけに行くようなこともあったり、
私が娘のご飯の支度をしている時は、娘の話し相手にもなってくれて助かりました。
うまく場を和ませて下さるので、終始カフェで話しをしているような雰囲気でとてもスムーズに取材は進みました。
ダブルケアの取材に関わって間もないとのことでしたが、細かいところまで熱心に聞き取りをされていて、このプロジェクトへの並々ならぬ思いが感じられました。
後日、取材とは別に写真撮影をしたのですが、この時の写真は本プロジェクトのメイン画像?として使用して頂いています。
そうと分かっていればもう少しいい構図で…
もう少しいい写真を…
と思うところではありますが(笑)
偶然にも白い服、白い部屋の壁、日中で明るい部屋、というものが功を奏し、
ダブルケアに向き合う中で見つけた「光」の部分を、ギリギリ表現できているのではないか…?と我ながら思っています😂
当時、数人のメンバーで手分けをしながら、全国各地のダブルケアラーを取材されていたそうですが、母の介護に合わせて予定を組んでもらっていたので、都合上、近隣のホテルに宿泊して頂くこともありました。
母が体調を崩した際でも、何度もスケジュールを調整してくれました。
それが原稿の締め切り間近だったとしても、私を焦らせるような言動は一切なく、むしろ母の体調を気遣う言葉までかけてくれて、本当にこの方が担当で良かったなと思いました。
記事の反応

自分がWebサイトや新聞に掲載されるなんて考えたことがなかったので、記事を見てもどこか現実味がなく、他人事のような不思議な感覚を覚えました。
肝心の記事の内容ですが、ほぼ取材時に話したことと相違なかったと思っています。
むしろ、取材時の私の足らない言葉をうまく汲み取って表現してくれて有難いぐらいです。
友人の中には、実際に新聞を買ってくれた人や、web登録して有料記事を読んでくれた人もいました。
また、記事掲載は、学校にもお知らせしました。
学校内でどこまで共有されたかはわかりませんが、生徒の中には、私のように我が子だけに120%力を注げない状況の保護者がいるかもしれないことや、
そんな親を間近で見て、自分の悩みを親に相談できずに1人で抱えてしまっている子供がいるかもしれないこと、
なんならヤングケアラーに近しい状態になっている子供が隠れているかもしれないこと、
そのように、学校にいる時の姿だけでは見えてこない部分に、目を向けてもらうきっかけになったらと思っています。

いくらニュースで騒がれたとしても、自分の身や自分に近いところで事が起きないと、大変さを実感することも、その状況を理解することも実際は難しいですよね。
でも、私は、ダブルケアが身近な場所で起きていること、近くまで迫ってきていることを知り、今そうでないご家庭でも、自分事として考えて欲しいなと思っています。
30代、40代は、低年齢の子どもがいたり、これから結婚を考えたりと、まだまだ親を頼りにしたい世代でもあります。
親が介護状態になるなんて考えたくもないし、親としても、「まだまだ元気だよ!介護なんて失礼な!」という想いもあると思います。
しかし、それが仇となるかもしれないのです。
私たちの記事をきっかけに、親の介護が必要になったらどんな生活になるのか、20代、30代、40代の方にも考えてみて欲しいなと思います。
孤独?孤立?いや…孤絶!

私の記事のタイトルには、「孤絶」という普段はあまり使わない強い言葉が使われているのですが、これに関しては、私の言葉ではありません。
記者さんが考えて下さった言葉だと思いますが、お陰で、危機意識をより強く訴えることが出来たのではないか、と思っています。
なので、私自身、このタイトルを見て、
「そうか、私ってここまでの状況だったのか…」
と改めて気づかせてもらった良い機会でした。
母は、後遺症として、脳血管性認知症や高次脳機能障害がありましたが、暴言をはいたり、機嫌が悪くなるようなことは一切ありませんでした。
介護サービスをフルで利用することで、介護に関して頭を悩ませることもありませんでした。
娘も、心のバランスを崩して不登校ではありましたが、医療機関には繋がっていたし、家族や物に八つ当たりすることもありませんでした。
社会的に見れば「孤絶状態」だったのかもしれませんが、比較的穏やかな状況だったので私自身もそれに慣れてしまい、感覚が麻痺していたのかもしれません。
ちなみに、孤絶の言葉の意味を調べてみたのですが、
孤絶(読み)コゼツ
孤絶(コゼツ)とは? 意味や使い方 – コトバンク (kotobank.jp) 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
デジタル大辞泉 「孤絶」の意味・読み・例文・類語
こ‐ぜつ【孤絶】
[名](スル)一つだけ離れて取り残されていること。
世間とのつながりがなく孤立していること。
「大陸から孤絶した島」「都会から孤絶した山村」
「世間との繋がりがなく孤立していること」
これはまさにですね。
「大陸から孤絶した島」
これも本当にそうだなと。
社会から切り離され、待てど暮らせど助けなどこない無人島から、いつ誰に届くかもわからないSOSをずっと送り続けているケアラーさんがあなたの隣にもいるかもしれません。
これからは、同じように孤独を抱えているケアラーさんを一人残らず救えるように、そもそも孤独を抱えることがないように、支援が行き届いてくれるといいなと思っています。
“かごの鳥”
これは、ダブルケアをしていて私が感じた正直な感想です。
というのも、母は医療ケアが必要なので、訪問介護(ヘルパー)を利用することが出来ませんでした。
どうしても私が対応しなければならず、結果的に、時間的な拘束がありました。
更に、娘は当時、自宅の庭にも出れない程に外出を怖がっていました。
徒歩10分以内の距離にあるスーパーやドラッグストアが、果てしなく遠く感じたのです。
近くにあるのに、行けない。
自分は動けるだけの体力も気力もあるのに、自分以外の理由で動くことができない。
「自宅」という場所から一歩も出ることが出来ず、窓から外を眺める事しかできない。
その自分が、鳥かごの鳥と重なったのです。
最終的には、窓の外に広がる「空」に救われ、社会との繋がりをもたらしてくれることになったのですが、
当時は、引きこもる、というより、自宅に閉じ込められているような感覚が強かったのをよく覚えています。
なぜ取材を受けたか
上にも述べましたが、自分の体験を通して、みなさんにも介護が身近に迫っているということを知って欲しかったからです。
でも、世間的には、

というようなことを私が望んでいるかのように感じた方もいたようです。
Yahooのコメント欄には、
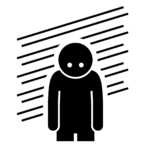
嫌ならやらなきゃいい。自業自得。
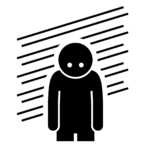
私ならこんな状態になってまで生きたいと思わないし、家族になんて見させない。
この親も親。
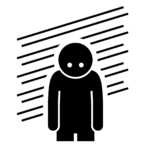
頑張ってる自分に酔っている。
褒めてほしいだけでしょ。
など、批判的な意見が書き込まれていました。
中には、「時系列がおかしい。この記事は信憑性に欠けている」というようなものまでありました。
こういったコメントを見る事は「百害あって一利なし」なので、Yahooサイトに関しては、掲載初日に一度見ただけで、以降は閲覧していません。
私は、なにも自分の大変さを伝えたくて取材を受けたわけではありません。
ただ、介護の現状、ダブルケアへの支援の必要性を訴えるには、まずは大変さを前面に出すしかなかったのです。

今、親が入院したら…
平日の昼間に面会や手続きに行ける人はいますか?
今、親が認知症を発症したら…
昼夜問わず生活支援を出来る人はいますか?
親の世話の為に、毎週末、実家に帰れますか?
今、徘徊の症状が現れたら…
一人で安易に外出してしまわないように、行動を見守れる体制は取れますか?
今、施設入居を考えた時…
入居金や毎月の費用を捻出出来るだけの貯金が、親にはありますか?
例え、今介護が必要ない状況だったとしても、そうなったら自分たちにどんな影響があるだろうか、と考えてみて欲しいなと思います。
誰もが介護をする側にも、
介護される側にもなるんです。
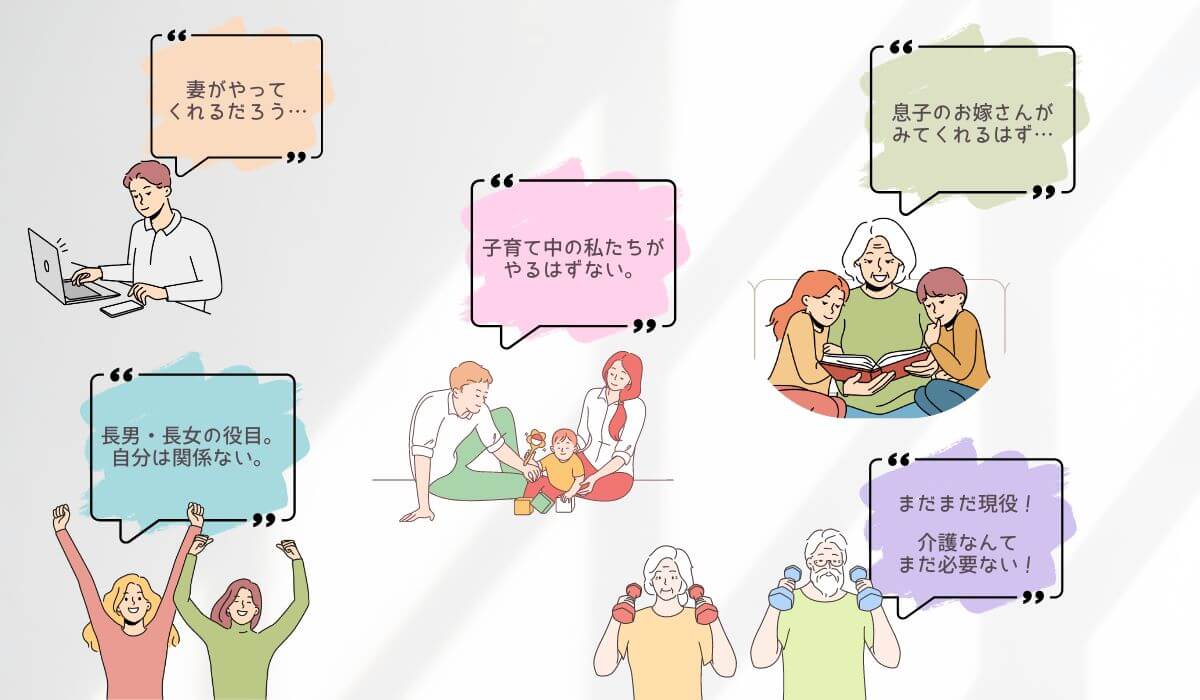
そうやって目を背けていられる余裕など、本当はもうないのだと思います。
そして、今回の毎日新聞の連載の中では、男性のケアラーさんも取り上げられていました。
近い将来、介護と仕事の両立に、男性が向き合わされることは明白であり、これまでの
男性は外で働き、女性は家を守る
という風習を、時代に合わせてうまく変化させていかなければいけない時が来ているなと感じています。
性別も、年齢も問わず、仕事もプライベートも充実させられる生活が基本で、
そこへ介護が加わってもバランスをとり続けられるような社会になっていくといいなと思います。

この毎日新聞のダブルケアの報道により、「ダブルケア」の言葉の認知度はグッと上がったと思います。
テレビなどでも取り上げられ、実際に、政治も動き始めました。
個人レベルでは決して届けることが出来ないところにまで、ケアラーの声が届いたことは純粋に嬉しく思いますし、そのきっかけを作ってくださった毎日新聞社様には感謝しております。
しかし、大切なのはこの後です。
社会全体としても、個人一人ひとりとしても、介護の未来を真剣に考えて行動していく必要があると思っています。
一人でも多くのケアラーさんの状況が改善されるように、これからも私なりに情報発信など出来ることをしていこうと思います。
~お知らせ~
Xにてお知らせしておりますが
先日、母が永眠いたしました。
これまで支えて下さった皆様
心温まるお言葉を下さった皆様
本当にありがとうございました。
これからも私なりのやり方で
介護やダブルケアに関する発信を
続けていこうと思います。
引き続きよろしくお願い致します。
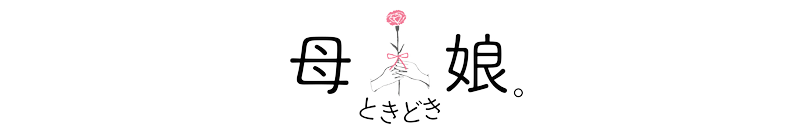
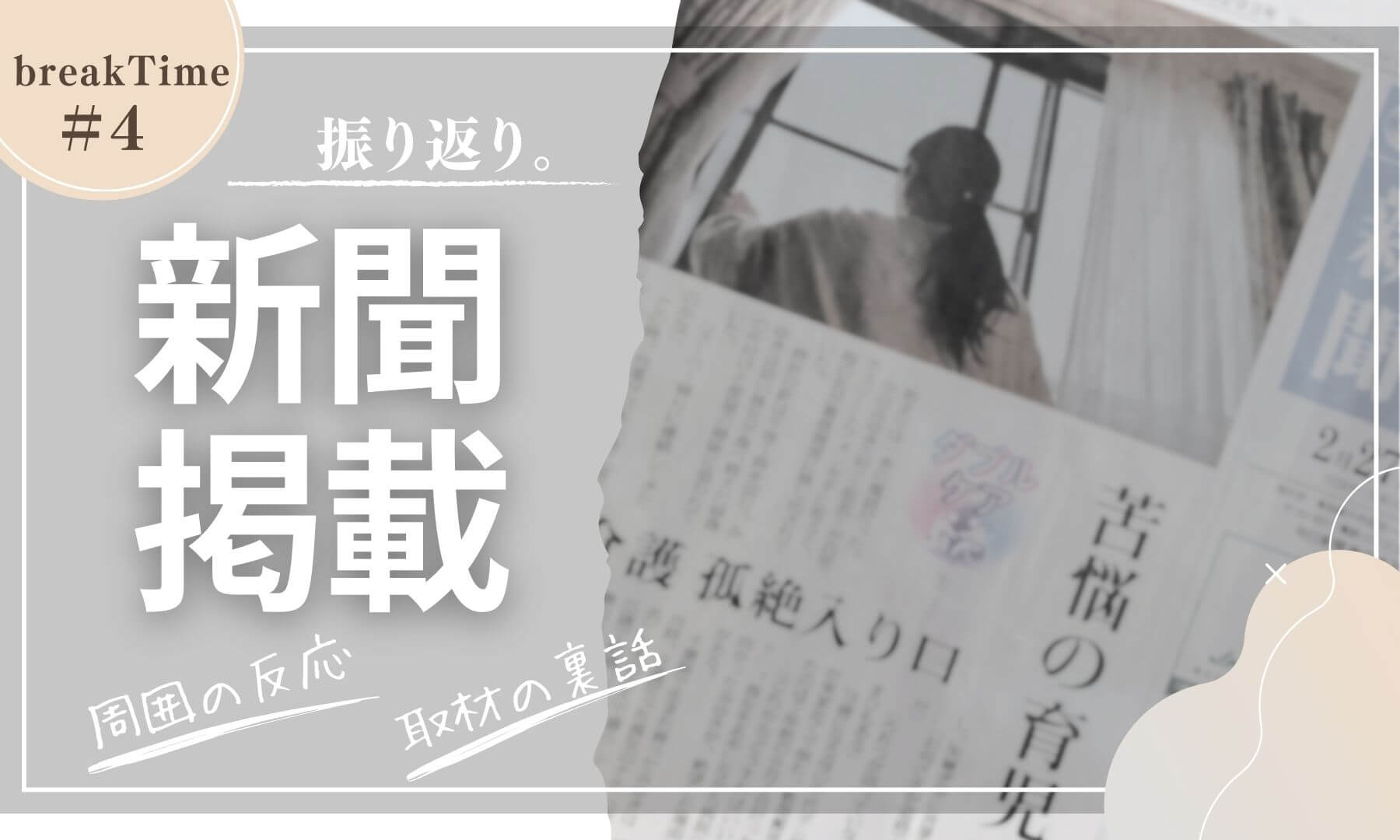
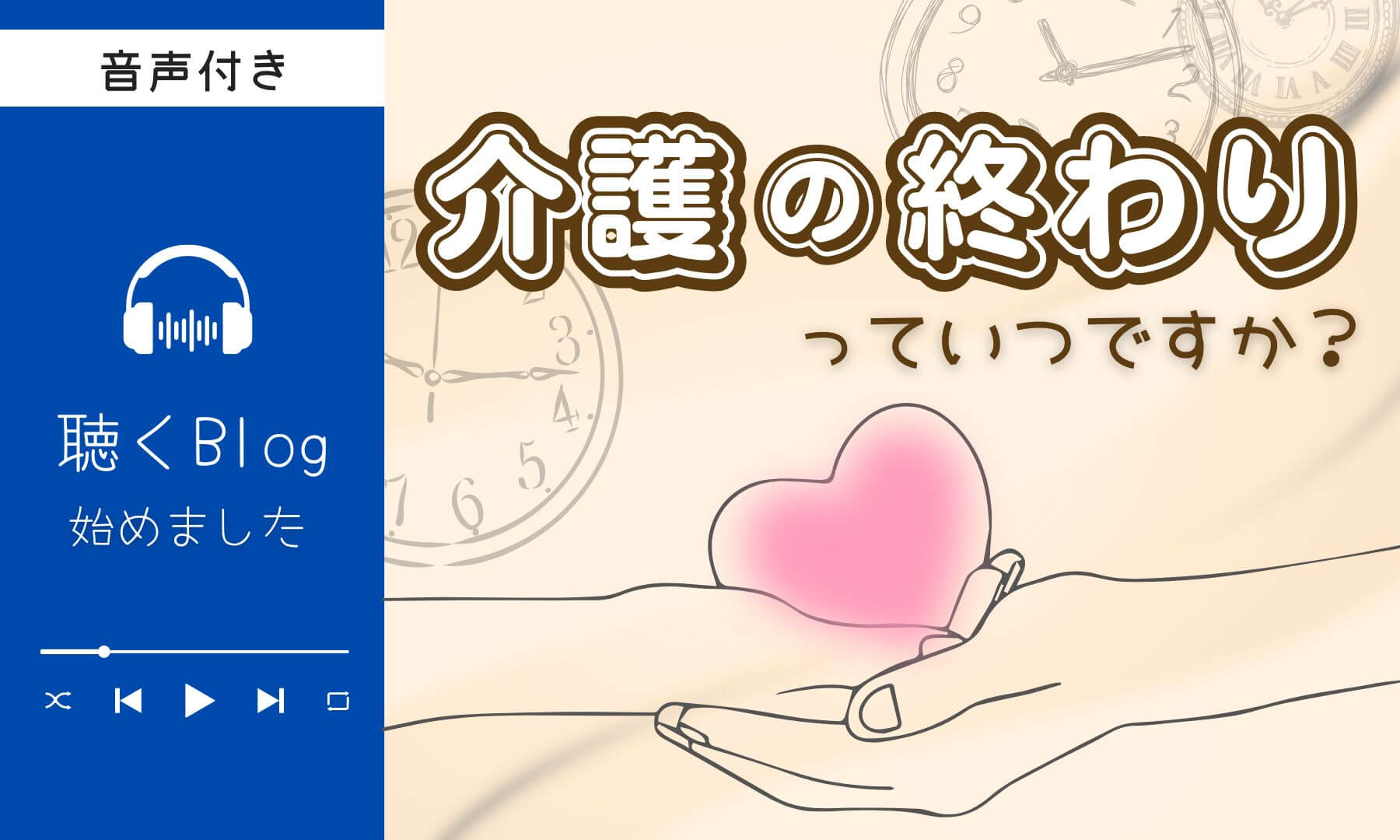
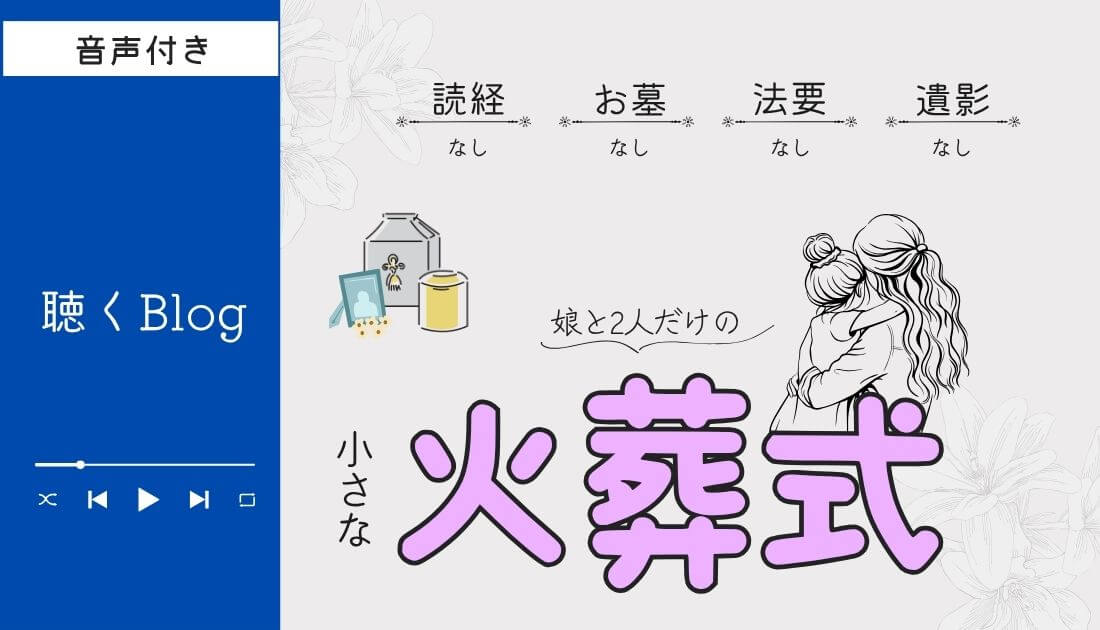
コメント