先日、DC NETWORK主催のオンラインイベントに『支援者』として初めて参加しました。
DC NETWORKは、医療分野の専門家で構成されているダブルケアの支援団体です。

『ダブルケア』と聞くと、まず高齢者の介護が浮かびますが、小児医療やヤングケアラー、男性ケアラーへのサポートなど多岐にわたってケアができる支援団体として唯一無二の存在ではないかと思います。
これまでの私の主な活動と言えば、Twitterとブログのみ。
『文字』でしか発信してこなかった私にとって、『話す』ことは初めてのこと。
勢いで2日間とも参加申し込みをしたものの、特に1日目は終始緊張して終わりました^^;
2日間とも違うメンバーの方とお会いできて、DCNETWORKに所属する方の職種や、代表のてらりんさんの人脈の広さに圧倒されました。
夜に開催ということもあり、不安の強い娘がどうしてもチラチラと画面に写り、ぬいぐるみを乱入させたり急に喋りだしたりとご迷惑をおかけしてしまったと思いますが、皆様の優しさに救われなんとか最後まで参加することが出来ました。
当日の様子はこちら↓

交流会

私は、母子・精神・産業の3チームと話すことが出来ました。
母子チーム
保健師の方や、小児医療を担当されている方がいらっしゃいました。
私自身、娘の発達障害で保健師さんには大変お世話になったのですが、市の保健師さんは基本的に乳児健診の時にしか会わなかったり、入園・就学すると一気に距離が遠ざかってしまうので、ダブルケアの家庭にとっては子供が成長しても保健師さんとつながれることは非常に心強いのではないかと感じました。
また、私がダブルケア千葉南を立ち上げる際に、Twitterで介護の体験談を聞かせていただいた際、子供にも特別なケアを必要としている家庭の多さにも驚きました。
本当は、保健師や医療の専門家に聞きたいことがあっても、相談に行く時間が取れなかったり、こんなことで病院にかかっていいのか?私がうまくやれば大丈夫かも?…などと病院へ行くことを躊躇ったり、相談出来ずにいる方も多いと思います。そういった方の、強い味方になってくれるんじゃないかなと思いました。
精神チーム
ダブルケアの支援として
何ができるだろうか
という精神チームの言葉がとても印象に残っています。
介護にも育児にも【心のケア】がすごく重要だと感じます。
しかし、実際は、心のケアは後回しにされている現状があります。
子供の健康を支える制度はあっても、母親を守る環境は整っていません。
要介護者の生活を支える制度はあっても、介護者を守る環境は整っていません。
家族内で、個人で、何とかするしかないのです。
悩ましいのが、介護が終わればそれで悩みがなくなるかといったらそうでもないということ。
介護が終わったら終わったで、
もっと何かできたのではないか…
もっと優しくしてあげたらよかった…
と後悔の念に悩まされている人が少なくありません。
また、2年も3年も待ってやっと親が施設入所できる順番が来たのに、コロナによる面会制限がネックで入所に迷いが出てきてしまったという話も聞きました。
それでも、自分の生活を守るために入所してもらったけれど、自分のせいで施設に入れてしまった…と懺悔のような気持ちで過ごしていたりすることもあるようです。
施設の親と面会する度に「家に帰りたい」と訴えられ申し訳ない気持ちになったり、身内からの心無い言葉に耐えながら介護を続けている方もいました。
介護の悩み、というのは介護中に限らず、介護が始まる前にもあるし、介護が終わった後でもしばらく続くものだということです。

現状、要介護者が亡くなれば、それまで関わりがあった介護サービスの方との繋がりは終了します。
これは当然のことです。
施設に入所すれば、介護者の負担は減り、悩みもいくらか解消されると思います。
これも実際そうだと思います。
でも、気持ちの切り替えはそんなにうまくいくものではないと思うんです。
これまで何年間も毎日のように、まるで家族のように関わってきた人たちが、亡くなったり施設に入ったと同時に自分の周りから姿を消す。
介護ベッドや車いすが返却され、すっぽりと空いたスペース。
行き場のない感情を誰に相談できるわけでもなく、自分で消化していくしかない状況は、下手したら、介護中より気持ちが落ちてしまうこともあるのではと思ったりもします。
身近で、大切な存在であればあるほど、後から湧き上がってくる想いも強いのではないかと思います。
例え、憎みながらの介護生活だったとしても…です。
事故や事件で家族を亡くした場合、遺族ケアやグリーフケアがあったりしますが、介護にも同様のものがあっていいんじゃないかと思います。
亡くなった後、施設に入所した後も、本当の意味で気持ちの整理が出来るその時まで、支援者と介護者が繋がれるようになるといいなと思いました。
産業チーム
介護と仕事の両立について話をすることが出来ました。
介護が始まると、仕事を継続できたとしても、正社員から契約社員やパートタイムへ変更して収入が減ってしまったり、キャリアの道を諦めることもあるでしょう。
私自身、現状、外に働きに出ることは難しいです。
過去、一度だけ働きに出ようと思ったことがありました。
娘が幼稚園に入園して順調に通えるようになってきた頃だったと思います。
当時は母も週2回デイに行っていたので、母がデイの日だけパートに行こうと考えましたが、週2日でOKという募集はなかなか見つかりませんでした。
ようやく条件が合う求人が見つかり、面接に行ったのですが、
子供の体調不良で
突然休まれるのは困る
休む時は自分で
代わりの人を見つけて下さい
土日のどちらかは出る
あなたも誰かの代わりに
出られるように
柔軟に対応してほしい
求人票には書かれていなかったことを面接で話されて、その場で、すみません…と辞退してきました。
「子育て中の方が多く働いています!」と掲げる企業でも、両親などのバックアップがなければ働くことは難しいな…とダブルケアである自分の立場の弱さを痛感しました。
支援の難しさ

他の支援者の相談事例を聞いていると、ちょっと友達に愚痴ったり、Twitterにつぶやいたりするようなレベルではなく、もっと生活に密接した深刻なものでした。
声のかけ方一つ、私にはなにも浮かびませんでした。
目の前で起きている問題を解決するには、目の前で起きていること以外の部分に目を向けなればいけないことが多い。
それは家庭の中だったり、心の中に入らないと見えてこない部分です。
デリケートな部分でもあり、ズカズカと入っていくわけにもいきません。
更に、支援者としては、相談に来た方の力になりたいと思っても、目の前で悩みを訴える人の言葉が全てでもなく、言葉の裏にある想いや複雑な事情が隠されていることもある。
支援者と相談者が少しずつ心の距離を縮めて、やっと見えてくるものや炙り出されてくるものがあって、そこにこそ本当の意味での解決の糸口が隠されているように思います。
話を聞いて終わりでもなく、一般事例からアドバイスをして終わりでもなく、個々に寄り添った相談や支援の形が必要なんだなと思いました。
少しずつ、確実に、ダブルケアの支援の輪は広がっています。
オンラインの普及もあり、住む場所が離れていても、人と人が繋がることが出来るようにもなりました。
でも、もっと…コンビニのようにフラッと気軽に立ち寄れる相談場所が全国各地にできたらいいなと思っています。
自分の住んでいる地域で、その地域に住む人同士で助け合って支え合っていけたら、ダブルケアの未来も悪くないんじゃないかなって思ったりもします。
いつの日も、人と人の繋がりや優しさを感じられる社会でありますように。
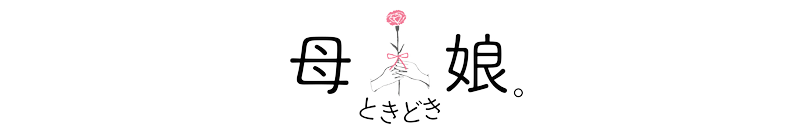


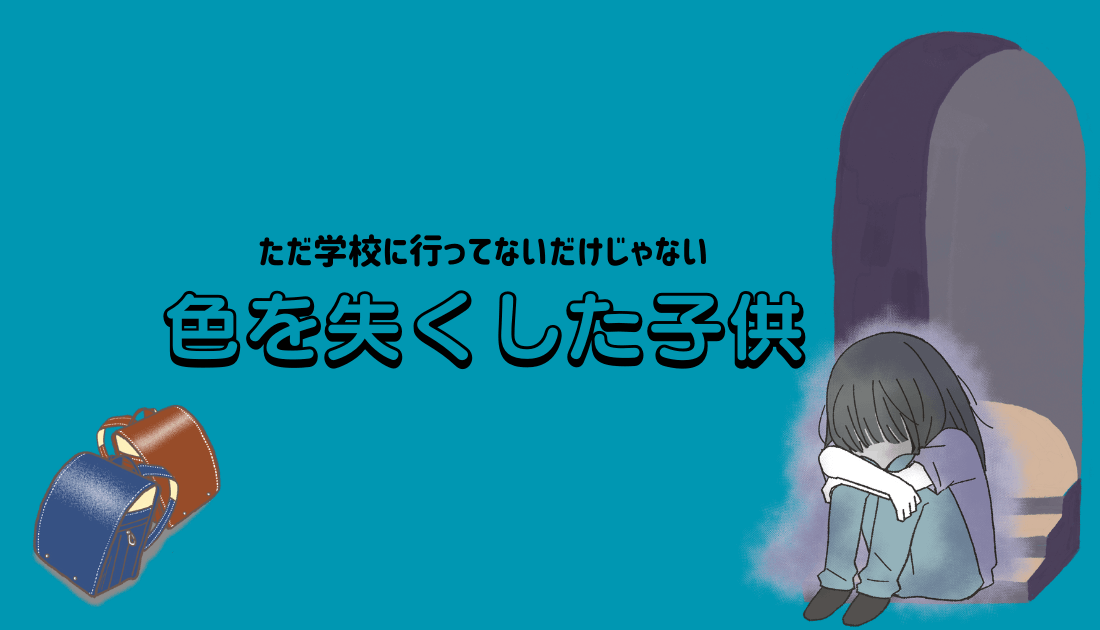
コメント